背景と課題
全社員が日常的にデータを活用可能とするための統合基盤の構築に着手
二輪車、四輪車、船外機など多様な製品を取り扱うとともに、企画から開発、生産、営業までの全プロセスを提供する、世界有数の総合モビリティメーカーであるスズキ。現在、同社が積極的に推進しているのが、全社員が日常的にデータを活用できる基盤の構築だ。
自動車をはじめとするモビリティ分野は、「自動運転」をはじめ、「電動化」「シェアリング」といった新たな潮流が押し寄せており、製品の多様化や異業種からの参入など「100 年に一度の大変革期」と呼ばれる激変の時代を迎えている。そのような変化に迅速かつ柔軟に対応するためには、データに基づいた適切な状況把握や意思決定が不可欠だ。
そうした状況の中、スズキは2022年、デジタル化推進部を新設し、より高度なデータ分析の実現および生成AIも活用するための環境づくりを進めている。IT本部長 デジタル化推進部長 野中彰氏は、「同時に、DX推進のためのスキル教育にも着手しており、その一環として、データ分析スキルを有したデジタル人材の育成を進めています」と語る。

スズキ株式会社 IT本部長 デジタル化推進部長
野中 彰氏

スズキ株式会社 IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課 主幹
菅沼 教多氏
だが、同社が高度なデータ活用を進めていくにあたっては、いくつもの課題があったという。その最たるものが、部門ごとにシステムが縦割りで構築されており、全社を横断したデータ活用が困難だったことだ。
IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課 主幹 菅沼教多氏は「これまでも様々な部門において、データドリブンな意思決定を目指したデータ分析・活用の取り組みが進められていました。しかし、必要なデータがシステムごとにサイロ化されており、各システムをシームレスに接続し、全社横断的なデータ活用を行うことが困難でした。そうした状況は、データの高度活用による新たな取り組みを行っていく上での妨げとなっていました」と振り返る。
事実、全社横断的なデータ活用が困難な状況は、各部門が業務革新を実現するための障壁となっていた。
生産本部 機種統括部 全体統括課の西谷諒太氏は「例えば、生産に関するデータが製造工程ごとに存在していたのですが、それらは各工程内でクローズドにされており、すぐに入手して活用することができない状況でした。そのため、生産工程全体を横断的に把握した上で、改善に繋げたり、効率化を図ったりすることが困難でした」と付け加える。

スズキ株式会社 生産本部 機種統括部 全体統括課
西谷諒太氏

スズキ株式会社 IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課
野田 宗裕氏
この状況は、データ活用に関する運用負荷を上昇させるだけでなく、ビジネスにおけるアジリティの確保、そして正確な意思決定の阻害要因ともなっていた。IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課の野田宗裕氏は「他部門が保有するデータを利用して分析を行おうとした場合、担当者が直接、相手側の担当者に連絡してデータを提供してもらっていました。そのため、必要なデータを入手するのに多くの時間や手間が発生していました」と語る。
グローバル営業統括部 海外事業業務部 業務プロセス革新課 課長の仲江川容亮氏も「リアルタイムでデータを取得できなかったことから、それが最新のものかどうか分からないケースが多くありました。同様に、マスターデータから変更が加えられていることもあり、そのデータが本当に正しいものなのか、判断がつかないまま利用せざるをえないことも少なくありませんでした」(仲江川氏)
これらの課題解決に向けて同社は、社内に散在する多種多様なデータを統合し、すべての業務において必要なデータを容易に入手可能な基盤の構築に踏み出す。各システムのデータを物理的に1つのデータベースに統合するというものだ。
「物理的なデータ統合では、システムとの接続に都度、ETLを開発しなければならず、データソース側にもデータ出力の対応などで協力をしてもらう必要がありました。開発には数週間かかってしまうケースもあり、ビジネス部門からの要求に迅速に応えられませんでした。加えて、開発したETLの継続的な保守メンテンナンスが発生する上、処理が増えるほどに運用負荷も大きくスケーラブルでないと感じていました」(菅沼氏)

スズキ株式会社 グローバル営業統括部 海外事業業務部 業務プロセス革新課 課長
仲江川 容亮氏
採用のポイント
Denodoを活用したデータ仮想化の導入を決定
伴走パートナーにジールを選択
これらの課題を解決するためにスズキが着目したのが「データ仮想化」である。データ仮想化とは、データを物理的に移動させるのではなく、ソースデータは元のシステムに残したままで、論理的に定義されたビューを通してリアルタイムにデータを提供する技術だ。各データソースは論理的に統合されるため、データ仮想化レイヤー上でデータを検索すれば、利用者は必要なデータを取得できるようになる。また、物理統合方式のようなETLの開発・運用も不要であるため、ソース元となるシステムとの接続も迅速かつ容易に行えるほか、IT部門の運用負荷も大幅に抑制可能だ。
このデータ仮想化を実現するためのソリューションとして選択されたのが、Denodo Technologiesが提供する「Denodo Platform V8(以下、Denodo)」である。菅沼氏は、「Denodoを採用した理由は、既に市場で多くの導入実績を有していたことでした。また、DenodoのデータカタログはデータをExcel形式などで取得したり、必要なデータを検索すればすぐに入手したりできるなど、データエンジニアやパワーユーザーだけでなく一般ユーザーが直接データ活用をする仕様となっており、これであれば全社活用を進めていけると判断しました」と強調する。
そして、Denodoの導入パートナーとしてスズキを伴走支援したのが、Denodo日本法人設立当初の2019年からDenodoのパートナーとして国内トップクラスの導入実績とナレッジを保有するジールだった。
「Denodoのパートナーの中でもジールはエクセレントカンパニーの位置づけにあり、かつ、国内での導入実績が最も多かったことが採用の理由です。また、これまでもジールは数多くの企業のデータ活用やDXの取り組みをサポートしており、今後、スズキが新たな取り組みを進めていく上で、Denodoのノウハウだけに留まらない、データ活用に関する豊富な経験値をご提供いただけると期待しました」(菅沼氏)
導入のプロセス
PoCをはじめとしたサポートを提供しDenodoのスムーズな導入を支援
スズキはジールのサポートのもと、2022年9月からDenodoのPoCを実施、同年12月には導入を決定する。その後も、引き続きジールの伴走支援により設計から環境構築を行い、2023年4月から全社向けにDenodoの展開を開始した。
菅沼氏は、「Denodoの導入にあたって、PoCから設計、インストールなど多方面にわたってジールに支援してもらいました。自由度が高いツールなので、当初はどのようなポリシーに基づいて仮想データベースを構築すればよいのか、設計で苦労した部分もありました。そのような中、ジールからはDenodoのコンセプトや機能の説明に加えて、他社事例に基づくベストプラクティスも紹介してもらえたため、設計に必要なノウハウを取得できました」と評価する。
プロジェクト推進・技術支援のポイント①
スズキが抱えていた課題を洗い出し改善点を抽出するとともに、PoCによる効果検証も実施

株式会社ジール アライアンス本部 アライアンス推進部 マネージャー
斉藤 宏
今回のプロジェクトでのサポートについてジールの斉藤宏は次のように説明する。
「従来の物理統合方式に起因する、データ作成工数の負荷と手間などの課題を解決し、より柔軟なデータ配信を実現するため、まずはDenodoのPoCを提案しました。そしてPoCを実施するにあたってはシナリオを検討し、スズキ様の課題を再認識するとともに、Denodoの機能についての技術的支援も実施しました」(斉藤)
なお、PoCでは「Denodoにより、現状の課題として認識している点が解消可能か、また、そのためにどのような運用工数・体制が必要となるのか」「Denodoに関する知識・スキルアップを通じて、どのようなビジネスシーンや領域で活用可能か」を主な検証項目として策定。その上で、機能や運用方法、セキュリティの確保等、多方面にわたる検証がジールの支援のもと、行われた。
プロジェクト推進・技術支援のポイント②
本番開始後も手厚いサポートを提供し、スズキの継続的なDenodoの活用を支援
PoCを経てDenodoの環境が構築された後も、プロジェクトが無事本番運用を迎えられるよう、引き続きジールによるサポートが提供された。
斉藤は「カスタマーサクセスという立場から、定期的にスズキ様、およびDenodo社も交えながらミーティングを実施し、なにか問題が生じた場合にもすぐに対処できるような体制づくりに取り組みました」と語る。
「なお、本番運用開始以後もスズキ様が継続的にDenodoを活用できるよう、ジールは運用支援に加えQA対応も実施するなど、引き続きサポートを提供しています」(斉藤)
導入効果と今後の展望
部門間でのスムーズで迅速なデータ連携で社内におけるデータ活用が加速
Denodo V9への移行でAI活用も視野に
Denodoの導入により、スズキのデータ活用は加速度を増している。野田氏は、「BIツールとDenodoを連携させており、ユーザーはDenodoのデータカタログから必要なデータを探し出し、取得できるようにしています」と説明する。
仲江川氏は「これまでは必要なデータを入手して分析するためには、ETLを介してCSV形式で取り込み、さらに分析用のデータベースに書き込む、といった複数の手順が必要でした。かつ、そのための仕組みを都度、データソースシステムの担当者に依頼し、用意してもらっていました。Denodoを活用することにより、DenodoとBIツールを接続すれば、最新の正しいデータを用いた分析がすぐに行えるようになりました。例えば、『このデータを分析で使いたい』といった場合、その環境を用意してもらうのに10営業日かかっていたものが、Denodoに接続済みのデータであれば、最短ゼロ秒にまで短縮されます」と評価する。
また、部門間を横断したデータ活用が行えるようになったことで、部門間の連携による業務全体のプロセスの最適化も期待されている。西谷氏は「Denodoを通じて営業部門が保有している販売計画や実績のデータを参照可能になると、適切な生産計画の立案に役立てられるようになると考えています」と話す。
現在、社内の様々な部門においてDenodoを利用したデータ活用が拡大しており、各部門からのデータ活用に関する相談件数は、2024年4月~9月の63件から2024年10月~2025年3月には126件に倍増している。
一方、ITシステム部の開発や運用にかかる負荷も抑制されている。IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課 佐藤文香氏は「システム別に様々な種類のデータベースを活用していますが、Denodoからは、すべてのデータベースに容易に接続できるため、ユーザーからのリクエストにも迅速かつ容易に対応できます」と評価する。
現在、スズキは最新版である「Denodo V9 Enterprise Plus」へのアップグレードを完了した。アップグレードの目的は、Denodo V9に実装された自然言語クエリのサポートや検索拡張生成などのAI機能の活用だ。これにより、さらなるデータ活用の民主化を加速させていきたいという。
その一方で、社内だけでなく社外のデータも分析に活用するため、国や自治体が公開しているオープンデータを加工して配信・提供するジールのサービス「CO−ODE(コ・オード)」の導入も進めている。
Denodoの採用により、全社横断的なデータ活用に向けた取り組みに大きく弾みをつけたスズキ。現在では、部門の担当者だけでなく、マネジメント層のデータ活用に対する意識変革も進んでいるという。

スズキ株式会社 IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課
佐藤 文香氏
野中氏は、「近年のモビリティ分野における環境の変化の中では、全社員自らがデータを活用し、いち早く現実を把握する力を獲得することが不可欠となります。そうしたことから、スズキは研修などを通じて経営層にもDenodoやBIツールに触れてもらい、データ活用の必要性を理解してもらうような取り組みを進めてきました。その結果、データ活用はIT部門だけでなく自分自身の課題であり、データを自分事として自身が使いこなせなければならない、という意識が醸成されています」と強調する。
最後に菅沼氏はスズキにおける今後のデータ活用の展望とジールへの要望について次のように語った。
「現状は、まだまだ全社に存在するデータソースからすれば10%もカバーできていないと考えています。ただDenodoを使えばすぐに接続ができるので、データ統合の網羅性を追うよりも、まずはユーザーが業務課題を解決することを優先し、リクエストが寄せられたデータソースへの接続に加えてその課題解決までのサポートを優先的に行っています。そうした中で、引き続きジールにはDenodoに関するサポートに加え、社外のデータを活用する事例など、スズキのデータ活用をさらに加速させるような提案を期待しています」
(写真左から)
スズキ株式会社
IT本部長 デジタル化推進部長 野中 彰氏
グローバル営業統括部 海外事業業務部 業務プロセス革新課 課長 仲江川容亮氏
IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課 野田 宗裕氏
生産本部 機種統括部 全体統括課 西谷 諒太氏
IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課 佐藤 文香氏
IT本部 ITシステム部 開発基盤・モデリング課 主幹 菅沼 教多氏
株式会社ジール
アライアンス本部 アライアンス推進部 マネージャー 斉藤 宏
※本事例内容は取材当時のものです


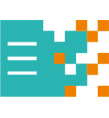 ZEAL DATA TIMES
ZEAL DATA TIMES

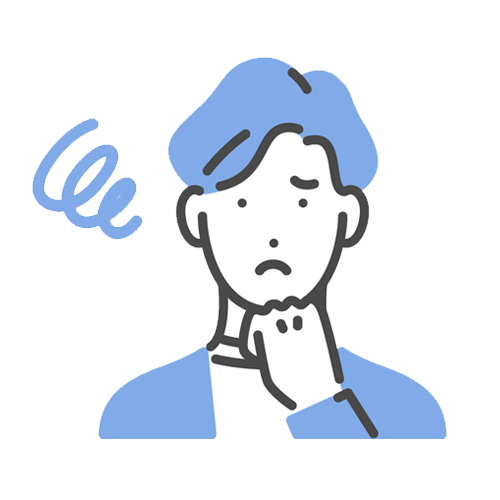












 CO−ODE
CO−ODE