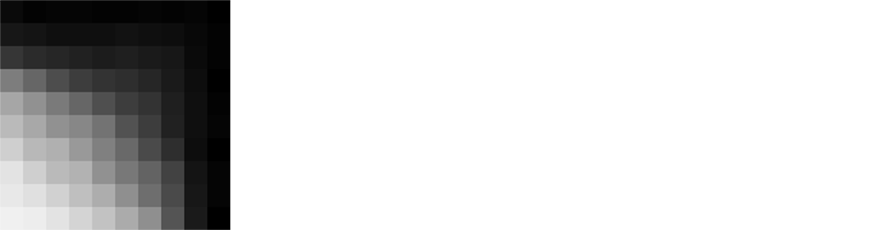データプラットフォーム×先端技術
データプラットフォームのリーディングカンパニーとして業界を牽引してきたジール。
そんなジールだからこそできる先端技術の活用方法とはなんだろうか。今後どのような可能性が広がっていくのだろうか。
当社の中でも先端領域を扱っている部署に所属する3名の社員に、先端技術をテーマに自由に語ってもらった。
参加メンバー
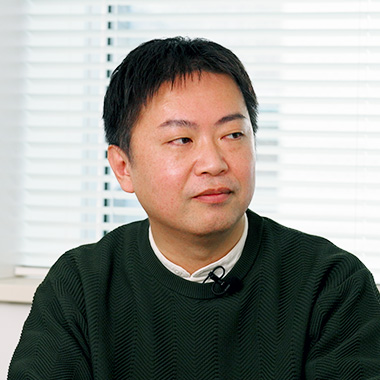
鈴木
SIerに7年ほど勤務し、システム開発、サーバーインフラの構築、自社製品の企画開発などを担当。その後大学院に進学し、2015年にジールへ転職した。入社後は企業へのAI・データ分析関連のクラウドサービス構想策定支援、提案、構築など幅広く実施。現在はDXを推進する専任組織に所属し、まずはジールの社内DXを推進中。

橋本
2018年大学卒業後、ITコンサルティングファームに入社し、コンサルタントとして企業のBI・AI活用、DX推進に関わるプロジェクトに複数参画。
2021年ジール入社後、デジタル領域におけるコンサルティング、データエンジニアリング、データサイエンス専門ユニットにて、業界業種問わずデータ基盤構築、データ利活用(可視化、機械学習)を中心に、DX推進に従事。
2021年ジール入社後、デジタル領域におけるコンサルティング、データエンジニアリング、データサイエンス専門ユニットにて、業界業種問わずデータ基盤構築、データ利活用(可視化、機械学習)を中心に、DX推進に従事。

田畑
2017年大学卒業後、メーカー系SIerに入社し、業務システムや認証システムのアプリ開発エンジニアを経験。AIに興味を持ちデータ活用ができる人材になりたいと思い、2021年ジールに入社。
データを扱うことの難しさに苦戦しながらも、自然言語処理を活用した業務改善支援やデータ分析基盤のアーキテクチャ構想のコンサルティングなどを担当。現在ではプロジェクトマネージャーとして幅広い案件に携わっている。
データを扱うことの難しさに苦戦しながらも、自然言語処理を活用した業務改善支援やデータ分析基盤のアーキテクチャ構想のコンサルティングなどを担当。現在ではプロジェクトマネージャーとして幅広い案件に携わっている。
Q.ジールに入社してからのキャリアを教えてください。
- 橋本
- 私は入社3年目ですが、当初少しだけプリセールスを挟んだ後、DatabricksやSnowflake、あとは3大クラウド全般の案件などに幅広く携わっています。現在はSnowflakeのプロジェクトとAzure Machine Learningを使った時系列予測のプロジェクトを進めています。
- 田畑
- 私も橋本さんと同じく入社3年目です。最初のうちは地に足の付いたデータエンジニアリングを経験した後、AI系の案件やデータの利活用を支援する高度な案件に携わっています。最近ではプロジェクトマネージャーも担当するようになりました。

- 鈴木
- 私はジールに入社して9年目です。最初はお客様にBIツールを導入する業務を2年ほど担当し、その後は分析や機械学習の専門部署が立ち上がるタイミングでそちらに移籍しました。データ分析やAIのPoC実証実験、データ基盤の構築などを中心にコンサルティングから実装まで幅広い業務を行っています。
- 橋本
-
前職のITコンサルでは上流がメインで、実装などを経験する機会がありませんでした。
ジールでは地に足の付いたデータエンジニアリングをプロジェクトベースで学ぶことができ、仕事に対する解像度も格段に上がったと感じています。

- 田畑
-
私は前職がアプリケーション開発で、逆に上流の要件定義や企画提案がやれるようになったのが大きな違いです。
自分の裁量で幅広い仕事ができ、マネジメントや提案活動を通じて成長を実感しています。
- 鈴木
- 私はジールに入社したことで、企業のデータ活用について深く学ぶことができましたし、データを使ってお客様に必要なものを提案する中で、期待に応える楽しさを知ることができたと思います。

Q.ジールに入るまでのキャリア、
前職との違いは?
Q.これまで携わった先端領域の案件を教えてください。
- 橋本
-
現在行っているAzure Machine Learningを使った時系列予測の案件です。
アルゴリズムの選定やモデルに関してはベンダーから提供されるサービスが進化しており、AutoMLのAPIを使えたり、ManyModelsで1回のAPIのコールで多数のモデルを作れたりするため、SKUごとにモデルをデプロイすることは比較的容易です。
一番大変なのは「データをどう精緻化していくか」ですかね。お客様にお願いしないといけないことも多く、伴走型で協力しながらモデルを作っていくのに苦労します。機械学習やAIといってもデータエンジニアリングの部分がついてきますし、前処理などもあるためカバーする領域がとても広い。難しいですが、その分やりがいも大きいです。

- 田畑
-
私の場合は、現在取り組んでいる自然言語処理を使って業務改善や効率化を目指すプロジェクトですかね。
とある製造業様の案件ですが、失敗事例や事故事例のデータをインプットしてクラス分類をしたり、人が書いた事故原因を機械学習で要約して原因が判別しやすくする仕組みを構築しています。
文章の要約には精度の高い生成AIを活用しています。リリースまでに1年ほどかかりましたが、お客様の中でもゴールが定まらない中で仮説を立て、伴走しながら一緒にゴールを見つけて走り続けることができました。
- 鈴木
-
私は2人のようにAI系の仕事も行っていますが、少し違う分野でいえば、AIを活用するための全社データ基盤の構築などを手掛けています。
何が正解なのかを選定するコンセプトの策定フェーズから支援しており、大企業の案件では、グループ会社の一番下のレイヤーの情報を上まで円滑に届けるお手伝いをすることが多いです。それぞれの会社の情報をグループ統括まで届ける手間を減らすのが第一段階で、そこから情報を見える化したうえで意思決定を適切に行うためのデータ活用を進めていくのが第二段階といった感じですかね。

Q.なぜジールが先端技術を扱うのか?
Q.ジールは今後どうなっていくか、
方向性や課題について教えてください。
- 田畑
-
これからもIT業界、とりわけデータ業界のトレンドを追いかけ、先端を走り続ける企業になると思っています。
昨今はデータ利活用の価値が格段に高まっていますし、今後もこの流れは加速していくと見ています。
- 鈴木
- データエンジニアリングの重要性みたいな部分は感じていますか?
- 田畑
- 感じますね。データエンジニアリングを抜きにしてデータ利活用はできませんから。

- 鈴木
- 生成AIが急速に広まっていったり、少し前だと深層学習が大きな注目を集めたりする中で、データ活用ができる分野はどんどん広がってきたと感じます。以前は社内データが見れるだけで満足だったお客様が、「他のデータも組み合わせて分析したい。そうしないと競争に勝てない」とおっしゃっていたりします。この分野をずっと見続けてきたジールは、お客様にベストプラクティスを伝えられる会社であり、いろんな価値を提供できると感じています。
- 田畑
- そうですね。お客様の需要という意味では、高さもあるし、幅もある。需要の体積がどんどん増え続けていくイメージです。
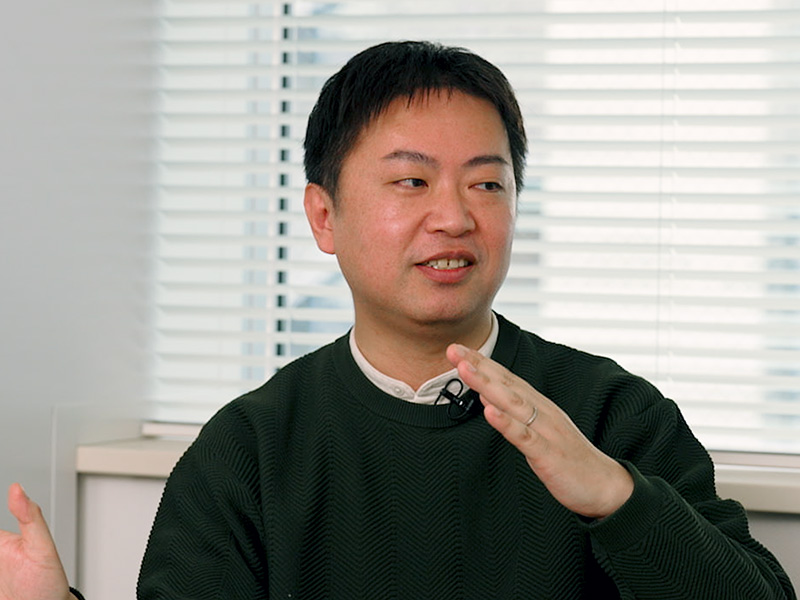
- 橋本
-
私も追い風だと思う一方で、アドバンテージがあるうちに他社に追随されない価値の幅や深さを身に付ける必要があるとも感じます。
そこで現在は、業務時間内で勉強会を開催して、先端技術の知見を深める取り組みなども始めています。
- 鈴木
-
伴走型にいち早くシフトしたところも大きいですよね。「ジールにすべてお任せください」ではなく「必要なところだけジールを使ってください」というスタンスに変わってきた。データ活用は「やってみるまで効果が分からない」と言われることが多い中で、まずは試しに取り組んでみようというお客様にも柔軟な提案ができます。
最近ではアドバイザーとして入る提案も増えてきてますし、今後もお客様の幅広い需要に応えていける会社を目指していければと思いますね。

Extra contents
今回参加した3人に、
今注目している先端技術について、
最後に語ってもらいました。
今注目している先端技術について、
最後に語ってもらいました。